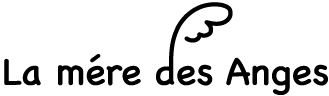1.コットン(綿花)の世界史
メキシコに遺跡があるアステカ文明が、およそ8,000年前に繊維を生産する目的でコットン(綿花)を栽培したのが、綿花栽培の最古の記録であるという説があります。(それ以前、マヤ文明でミイラを包んでいたものは、綿であると言われてます。)また、最も古い木綿生産の痕跡は約7000年前(紀元前5千年紀から紀元前4千年紀)のもので、インダス川の周辺で発展したインダス文明の住民によるものと言われています。インダス川流域の木綿産業はかなり発展し、そこで生まれた紡績や機織りの技法や、種子は、西暦が始まる以前に、東は中国、西はインドから地中海世界、さらにその先へと広まったと言われています。
代表的産地の歴史
- インドでは古くから綿が栽培されいると言われています。(遺跡からは紀元前2500年-同1500年の綿布が発見)インドの綿製品はアラビア商人によってヨーロッパにもたらされました。
- エジプトの綿は、紀元前200年よりも以前には綿を利用した証拠が発見されていませんから、現在のエジプト綿は13~14世紀に栽培が始まったと言われています。
- 南アメリカの綿は、ペルーで紀元前1500年頃から利用されており、ブラジルでも古くから原住民によって利用されてきた歴史があります。
- アメリカ合衆国の綿は、イギリスがパナマで栽培したインドの綿が、1740年頃にバージニア地方に伝わって栽培されるようになったものです。
- 中国へは後漢の57~75年頃(1世紀)にインドから綿布がもたらされたと言われています。綿の種子は10世紀に伝えられましたが当初は観賞用で、本格的な栽培は南宋の1125~1162年頃に始まったと言われています。
- 日本で綿が初めて栽培されたのは、『日本後紀』よると、桓武天皇の延暦18年(799年)、三河国に漂着したインド人がもたらした種子によるとされています。日本の綿の歴史は世界に比べて比較的浅く、全国に急速に普及するのは戦後時代以降、経済的栽培が始まったのは16世紀に入ってからであると言われてます。
[出典:平凡社『大百科事典』第15巻(1985年発行)、Wikipedia等参照]
調べてみるとコットン(綿花)の歴史は古く、人類の生存に欠かせないものとして、食料と同じように身近な植物であることがわかります。
コットン(綿花)生産量の現状
現在コットンは、生産されているほとんどは、発展途上の国や地域です。2017年のコットン生産量が多かった国を見ていくと、1位がインド(6,314千トン)、2位が中国(5,824千トン)、3位がアメリカ(3,876千トン)、4位ブラジル(2,885千トン)、5位パキスタン(1,089千トン)となっています。中でもイギリスの植民地時代に一時衰退したインドでのコットン生産量は近年増加し、以前1位だった中国を抜いて現在ではトップです。世界のコットン生産量の約27%はインドが占めています。また、農薬や化学肥料を使わないオーガニックコットンは、その半数以上がインドで生産されています。
[出典:USDA「World Markets and Trade 2021]
2.日本のコットン(綿花)の歴史
日本に初めて綿が伝来したのは8世紀末とされています。そこには延暦18年(799年)に、崑崙人(後に天竺人と名乗る)が三河国に漂着して綿種を伝え、その翌年に朝廷は綿の種子を紀伊などの国々に配り、試植させたことが記されています。しかし、このとき各地に植えられた綿の種子は定着することなく途絶えてしまいます。
[出典:日本後紀、類聚国史参照]
日本の着衣 木綿以前の時代
木綿が身近な衣料素材として普及するようになる16世紀頃まで、庶民が身につけていた素材はおもに麻、絹と言われています。(古代、中世を通じて民衆衣料の素材とされたのは麻、絹のほかに藤や葛、楮(こうぞ)などからとった繊維もありました)『日本書紀』などの古代の文献に「木綿(ゆふ)」とあるのは、現在の木綿ではなく、楮からとった糸と考えられています。また、古代から中古(中世・平安時代)にかけては、「綿」「真綿」とは絹糸のことを指していました。 特に麻の原料となる植物は苧麻(ちょま)と呼ばれ、イラクサ科に属し、山野に自生する多年草で、至る所で手に入ったようです。それを畑に植えて栽培し、衣料原料としていました。
現代の感覚からすると「麻」には高級感はあり贅沢品にすら感じますが、やはり、冬の素材としては使えません。しかし、木綿(もめん)がなかった時代では、寒い季節には何枚も重ね着をして寒さをしのぐしかなかったと言われています。
日本に木綿製品が伝わるのは14世紀以降ですが、朝鮮半島に木綿の種子が伝わったのも、14世紀後半の高麗末期であったと言われています。中国元朝に送られた高麗の使者が、帰路、中国で木綿を見てその種子を持ち帰ったのが発端となり、それから10年ほどのうちに朝鮮国内に広まったと言われています。また、中国で木綿の栽培と綿布の生産が行われるようになるのは唐の頃であり、宋末から元初の頃には江南にまで広まっていたものの、本格的に木綿栽培が発展期に入るのは14世紀末から15世紀初頃であったと言われています。
[出典:永原慶二『新・木綿以前のこと』参照]
史料上「木綿」と記されているのは14世紀中頃以降、南北朝・室町期に入ってからのものです。この頃の木綿はすべて輸入品であり、1406年に室町幕府が朝鮮国王に派遣した使節たちに与えられた賜物の中にも、青木綿や綿子が記されています。この頃から朝鮮木綿に対する日本側の関心と需要が急速に高まっていったと言われてます。 室町時代中期に入って日本側の木綿需要が急激に高まりだしたのは、木綿のよさの一般的認識のひろまりばかりではなく、兵衣として高い性能を持っていることが認識されるようになったからであると考えられています。応仁の乱(1467-1477年)はその状況に拍車をかけ、幕府をはじめ各地の戦国大名たちは競って朝鮮から木綿を輸入するようになります。 その後、木綿が朝鮮国内で深刻な品不足になると、木綿価格を引き上げたりしながら輸出制限をかけるようになります。 日本ではその対応策として中国からの輸入をはじめるようになります。16世紀の後半には輸入木綿は、中国木綿が朝鮮木綿を上回るくらいになったそうです。こうして日本での木綿は、貴族社会では高級布地として珍重される一方、民衆の衣料素材として、軍用に不可欠な素材(兵衣、幔幕、火縄等)に急速に広まっていったと考えられています。
[出典:永原慶二『新・木綿以前のこと』永原慶二「綿作の展開」参照]
国内木綿需要の拡大
江戸時代になると米に次いで最も重要な換金作物であった綿は、西日本各地で栽培されていましたが、なかでも畿内(特に摂津・河内・和泉)は最大の綿作地と言われています。その後、全国的な需要の増加によって綿価は高騰したために米価より有利になったので、綿作は17・18世紀を通じて市域全域に普及し、特に現在の阪急神戸線以北の武庫地区と、武庫川下流の新田地帯では全耕地の30~40%の綿作が出現しました。 綿作農家は稲作と菜種作とを組み合わせた経営で多収益をあげたと言われています。そして富裕な農家は綿作地帯の農村には広く形成され、また綿花を商う在村商人も活躍し、農村全体が繁栄しました。しかし幕末になると他の地方の綿作が拡大したため、綿価は下落し畿内の綿作は衰退方向に向かったとされています。やがて1890年代に機械紡績業が発展しはじめると、国内産綿花は技術的に不適合となり、輸入綿花に圧倒されたために綿作は最終的に消滅しました。
日本の近代紡績の誕生
日本の近代紡績の誕生は、明治15(1882)年に渋沢栄一氏の主唱にて設立された大阪紡績(現・東洋紡)が始まりと言われています。原料である綿花の供給は、一部の外国商社と手を組んだ商社に頼っていたため、価格や輸入量など不透明であったために、国内紡績会社として明治25(1892)年に日本綿花株式会社を設立することになります。その後、大正元年時点で全産業に占める紡績業の割合は5割に達していたため、日本綿花株式会社は原料を調達する事業で日本の産業に大きく貢献することになります。
日本綿花株式会社設立後、直ぐにインド、エジプト、中国からの綿花の輸入を開始したとされています。明治29(1896)年には、わが国初の米国綿輸入を手掛け、米国では日綿社員が日本人として初めてニューヨーク綿花取引所の会員として入会します。 中国では明治36(1903)年に上海支店を設立し、中国綿の取り扱いもトップとなりました。大正6(1917)年には、日本初のビルマ綿の輸入を開始し、精米工場を買収するなど、戦後も含めビルマは日綿にとって強い協力地域となります。また東アフリカにおいて日本企業初の綿花の試験栽培を実施し、これが日本の東アフリカ投資の第一号といわれています。第一次世界大戦が勃発すると豪州産羊毛の輸入が途絶えたことにより、アルゼンチン、ウルグアイ産の羊毛の輸入を開始しました。
日本の紡績業は製品である綿糸、綿布の輸出を拡大し、大戦時には世界最大の生産国であった英国からの供給が途絶えたこともあり、日本の製品輸出は急拡大し、膨大な外貨をもたらしました。日本綿花株式会社の喜多又蔵社長は、日本の紡績業および日本の工業発展への貢献が認められて、大正8(1919)年に開催されたパリ講和会議の4人の民間随行員の一人として選ばれています。欧州から帰国した喜多社長は、人造絹糸の将来性を見出し、日窒コンツェルンの野口遵と共に旭絹織(現・旭化成)を設立し、化学分野にも進出していくことになります。
[出典:日本双日歴史館 参照]